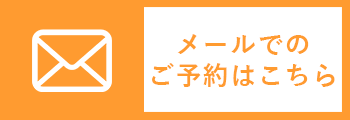口腔顔面痛オンライン相談での自己筋痛診査

口腔顔面痛診療は日本全国何処でも受けられるわけではないことから、数年前から口腔顔面痛のオンライン相談を受けています。診療ではなく相談としているのは、一度も対面診療せずにオンラインだけでは正しい診断、治療に制限があるからです。
オンラインでも神経障害性疼痛診査の為の感覚検査は通常の対面診査と同等に行えることを前述しました。https://wajima-ofp.com/blog_articles/1755509833.html
口腔顔面痛で最も一般的な筋・筋膜性疼痛診断のための筋圧痛診査は難しいです。オンラインでの有効な自己診査法を考えてみました。
- とりあえず、貴方の痛みのある側で頬杖をついてもらいます、その格好は手のひらに顎の先が上手く収まって頭の重さが支えられ、親指が顎の下、揃えた指4本で顎を包み、人差し指と中指が耳の付け根に当たっています。
- そのままの格好で、何回かかみしめてもらいます、揃えた指の中頃で波打つように咬筋が収縮します。その波打つ部分に指先を移動します、そして、また、何回かかみしめてもらい、指先でしっかり筋の波の頂点を確認しましょう。
- 指先を波の頂点に置いたまま、かみしめをやめて力を抜いてもらいます。筋肉の盛り上がりは消えましたが、指先でしっかり触ると少し硬い部分が残っています。指先に力をこめたままで、少しだけ、ゆっくり顔、頭全体を揺らしてみましょう。きっと、指先に触れる硬いコリコリした部分が行ったり来たり、場合によっては強い痛みを感じることもあるでしょう、痛みが強かったら圧す力を少し弛めましょう。少し痛みを感じる程度に圧したままで、数秒顎を揺らし続けてください、上手く顎を揺らすことが出来なかったら指先でコリコリをゴリゴリしてみましょう。どこか他のところに痛みが広がりませんかと関連痛を確認します。
- 次に、反対側で頬杖ついてもらい、手のひらに顎の先が上手く収まって頭の重さが支えられ、親指が顎の下、揃えた指4本で顎を包み、人差し指と中指が耳の付け根に当たっていることを確認しましょう。
- 痛みのある側と同様に、かみしめてコリコリを確認し、コリコリに指先を移動して、少し痛みを感じる程度に圧したままで、数秒顎を揺らし続けてください、上手く顎を揺らすことが出来なかったら指先でコリコリをゴリゴリしてみましょう。どこか他のところに痛みが広がりませんかと関連痛を確認します。
この二つの疾患をオンラインで何とか可能性の有無を詰めようとおもって、試行錯誤しながらオンライン自己診査法を検討しています。
2025年08月19日 15:42