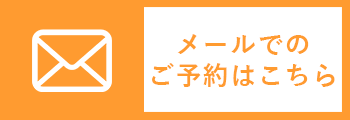痛覚変調性疼痛治療-患者さんを支えること
2024年はNociplasticPain(2017)、痛覚変調性疼痛(2021)とはどんなものなのかと痛み関連の人達の関心を集めました。今年はもっと具体的な話しが出てくるでしょう。期待します。
昨年は関心が高まった結果、まるで新しい痛みが見つかったように、しかしながら、心因性疼痛(国際疼痛学会では正式用語ではないらしい)が消えて、それに代わるわけではないと言われるが、途中経過として様々な用語(心因性疼痛から始まり、非器質的疼痛、中枢神経機能障害性疼痛など、精神科領域では身体表現性障害(疼痛障害))で呼ばれてきた痛みに中枢感作を主たるメカニズムとする正式名称が与えられたと言うことだと思っている。中枢感作は痛み神経系に使われる用語なので、痛覚変調性疼痛診断の際に検討される併発疾患である光過敏、音過敏、睡眠障害、匂い過敏、夜間頻回の覚醒を伴う睡眠障害、 疲労、 集中力の欠如、記憶障害などの認知的問題などは中枢感作とは言えないが、痛み系の中枢感作の他に脳機能全体が変調した状態と捉えるべき。問題は何故侵害受容系が変化してしまい、他の脳機能全般を巻き込むまでになるのかのメカニズム解明と現実的にはどのように治療するかである。
Kosecの最新論文(The concept of nociplastic pain—where to from here? PAIN 165 (2024) S50–S57)によると、薬物療法は神経障害性疼痛の薬物療法と類似している、ということで目新しいものは無く、トリプタノール、プレガバリンの投与とともに、TopDown発生因子の精神心理的ストレスが疑われるときはBiopsychosocialモデルとして心身医学的対応をすることに尽きる。認知的共感を目的とした傾聴で支えてあげることに尽きる
Biopsychosocialモデルとして心身医学的対応には各自の心身医学的対応トレーニングの程度により支えのレベルが異なるが、まずはこのような考え方を持つことが大事と思っている。患者さんを支えることにより自然治癒能力が発揮されて、良い方向に向かってくれる。下手な治療で邪魔してはいけない。
2025年01月07日 10:17