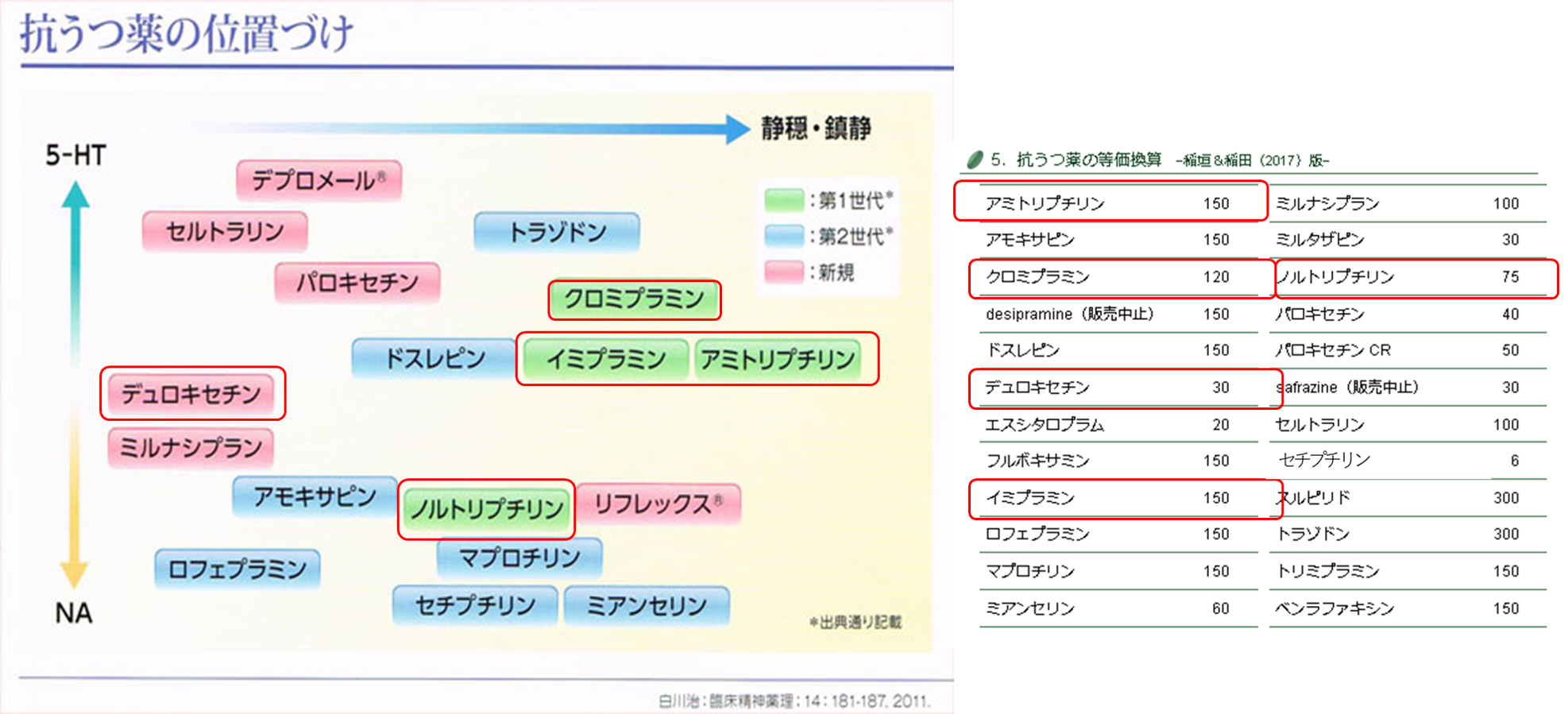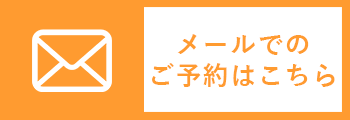抜髄か経過観察か 早期の判断が求められる
気がつくと10月中旬、来週は札幌出張。この時期は冬に向かう札幌と東京の気温差が大きい時期です。春にはまだ冬の札幌と春半ばの東京とで気温差が大きい時期があります。先週来、頭の中で興奮状態にあるのは歯内療法後の不快症状についてのびっくりの情報です。
この10月9日のタフツ大学Interdisciplinary Pain and Headache Roundsで歯内療法専門家のJennifer Gibbsの講演を聴きました。痛み研究で有名なテキサス大学Kenneth M. Hargreavesの大学院を卒業した人でENDO専門家で歯髄の痛みのメカニズムを神経生理、免疫学的に研究している人です。
1.知覚過敏は中枢感作によるものだろうと言っていました。象牙細管の動水力学性は歯の表面から象牙細管への刺激の伝導の話しであった、過敏反応は歯髄中の軸索反応連鎖の結果の知覚神経の過敏、反応性亢進が生じているということです。
2.歯内療法後、半年経過して痛み不快症状が残る患者の比率が5%位あって、その中で非歯原性歯痛であるものが3%位というNixdorfの有名な論文(2010)を紹介していました。そして、抜髄後の痛み、不快症状の誘因は術前三ヶ月以上続いた痛み、術中の痛みと言って、中枢感作が起こっているからだと結論していました。
歯内療法後の不快症状、痛みの原因が3ヶ月以上の術前痛という話しは、2005年Polycarpouの論文に書かれていてびっくりした内容と同じです。この論文の結論には、歯内療法成功後の持続的疼痛に関連する重要な危険因子として、1)術前の患歯部位からの疼痛が少なくとも3ヵ月以上持続していたこと、2)過去の慢性疼痛経験または口腔顔面領域の疼痛治療歴があること、および3)女性であることが挙げられていました。Polycarpou N, Ng YL, Canavan D, Moles DR, Gulabivala K. Prevalence of persistent pain after endodontic treatment and factors affecting its occurrence in cases with complete radiographic healing. Int Endod J. 2005;38(3):169-178. doi:10.1111/j.1365-2591.2004.00923.x
当時、これらの危険因子がどのような意味合いを持つのか全く判りませんでしたが、今現在になって、私の解釈では、術前痛と術中痛は最近のnociplastic painの発生メカニズムと挙げられているBottom UP(術前痛による持続的痛み刺激、結果として中枢感作)、Top Down(術中痛による不安感、恐怖感による扁桃体刺激による中枢感作)に該当すると考えられ痛覚変調性疼痛つまり中枢感作が生じているということになります。
歯髄の反応、しみる、痛いは歯髄の中だけで起こっているのではなく、当然中枢神経系の伝わって感じられることは理解出来ることです。ところが、歯髄の反応としてのしみる、痛いは神経系を通り過ぎているだけではなく、単純に言うならば神経系の要所、要所を荒らしてしまう、その結果、過敏になってしまい、中枢感作につながるのです。
知覚過敏、歯内療法後不快症状の原因が中枢感作と言うことで、3ヶ月以上の当該歯の痛みが危険因子であるとすると、症状があるのに3ヶ月以上経過観察すると言うことはあってはならないことになります。あらゆる診査をして、早期に抜髄するか経過観察するか決断が必要と言うことです。
2024年10月14日 18:39