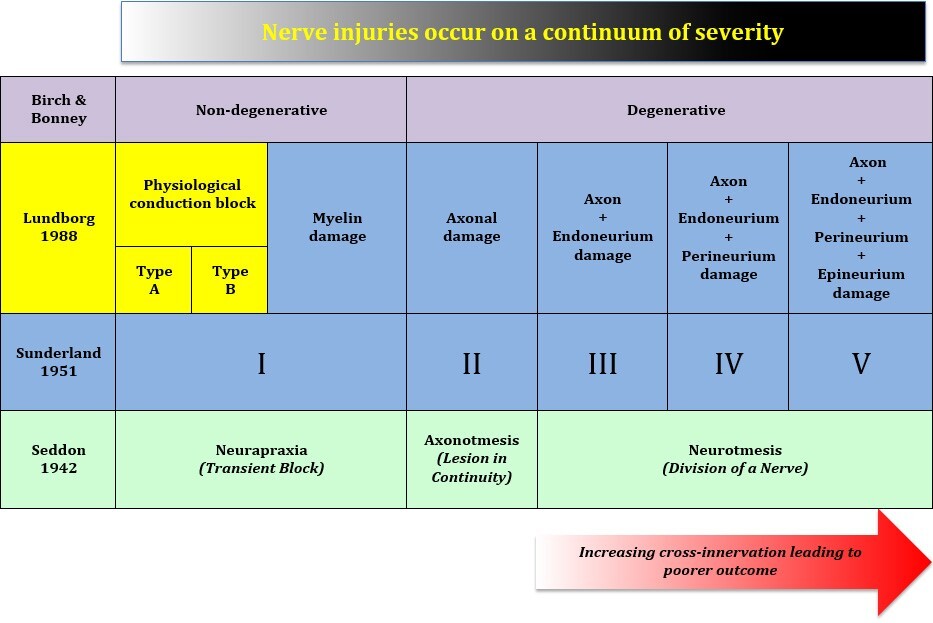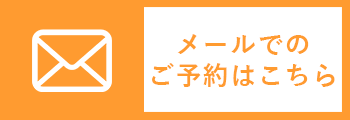私の口腔顔面痛診査は主訴にかかわらず全例に網羅的に診査を行っています。ここでは2.感覚検査が非常に有意義だった神経障害性疼痛症例を紹介するとともに、局所麻酔薬、神経刺激物質を用いた外用薬治療を紹介します。
症例3:33歳女性
主訴:右下76歯間部歯肉が熱いモノ、甘いものがしみて、食事を何回も中断する。VAS50
現病歴:10ヶ月前に下顎右側4根管治療終了後、下顎右側6に痛みが生じた。深い虫歯があるということで抜髄処置、根管処置終了し支台築造したがしみるのが止まらない。甘いモノ、熱いモノがしみて食事を中断してしまう。原因不明と言う事で、下顎右側埋伏智歯が原因の可能性があるとのことで抜歯したが、症状変わらず、下顎右側7の近心にカリエスがあるからそれが原因ではないかとも言われた。下顎右側7は生活歯で冷水痛無しであった
心理テスト:心理テスト:HADs(不安10点、うつ9点)、PCS(反芻18点、無力感15点、拡大視6点)
睡眠障害診査:入眠障害、途中覚醒あり
既往歴:無し、内服薬無し
局所診査:
1. 歯原性、非歯原性の診査:デンタル、パノラマレントゲン下顎右側6根尖透過像無し、打診痛なし、治療経過などから歯原性を否定。
2. 感覚検査:下顎右側6頬側歯肉触覚Dysesthesia、痛覚hyperalgesia、冷感覚低下、温感覚過敏、残感覚あり。甘み刺激過敏、残感覚あり。オトガイ部の感覚異常なし、舌の感覚左右差無し、味覚異常なし。顔面感覚異常なし
3. 脳神経検査:上記三叉神経右側第3枝温感覚過敏以外異常認められず。
4. 筋触診:左右咬筋、側頭筋に筋肥大、硬結、圧痛なし
5. 顎関節診査:ROM42mm、左右側下顎頭滑走正常 牽引、圧迫誘発テスト痛みなし
6. 咬合状態:明らかな異常なし
7. 診断的局所麻酔:頬粘膜浸潤麻酔により温熱感覚異常消失。
臨床診断:下顎右側6部歯肉神経障害性疼痛(温熱、甘味刺激にのみ感作)、原因不明、オトガイ部の感覚異常がないことから下歯槽神経の全体のニューロパチーは否定的、舌の感覚(三叉神経、舌咽神経)、味覚(顔面神経、舌咽神経)は正常であるのでラムゼーハントは否定、歯肉の外傷の記憶はなし。
患者への説明:歯原性の可能性は低いのでこれ以上カリエスの治療等はしないこと、歯肉に熱刺激をしたら、食事中の熱刺激による痛みと同様の痛みが再現されたことから、熱受容体が関連する神経障害性疼痛の可能性が高いことを説明した。いつもの痛み(Familiar pain主訴)が再現されたこと、病名の詳しい事は理解出来ないが、ほぼ納得出来ることから提示した治療が受け入れられた。
診断的治療:頬粘膜への診断的局所麻酔により温熱、甘味刺激による誘発痛を止めることができたので、末梢性と判断して局所療法を行うこととした。就寝時に2%リドカイン軟膏を患部に塗布してステントを装着して覆う。
1ヶ月後、オンライン再診、VAS50 熱いモノでの食事中断は変わらず、甘味の刺激は軽減しているとのことであった。局所療法の継続を指示。
3ヶ月後再診:VAS40 熱い食べ物で食事中断することはなくなった。敢えて熱いモノを下顎右側6部に付けて反応を確認してみると、痛みは弱くなっている。 感覚検査:下顎右側6部触覚Dysesthesia 痛覚hyperalgesia 冷感覚低下 温感覚過敏 残感覚なし。舌の感覚、味覚異常なし、左右差無し。
処置:就寝中ステントを用いた2%リドカイン軟膏塗布は有効と判断し、2%リドカイン軟膏に加えて、TRPV1(熱感受受容体)を積極的に刺激する暴露療法を意図して一味唐辛子を混ぜて塗布することを指導した。
考察:本症例は主訴として右下76歯間部歯肉が熱いモノ、甘いものがしみて、食事中に何回も食事中断する、と言うことから神経障害性疼痛が疑われた。私の口腔顔面痛診査は主訴にかかわらず全例に
網羅的に診査1-7を行っています。ここでは
2.感覚検査を紹介します。
この患者さんで有意義だったのは2、感覚検査です。基本的に左右同部位の比較をします。口腔内の感覚検査は触覚はミラーの縁と充填器の丸い部分で歯肉粘膜を擦過します。基本はMechanical Dynamic Hyperalgesia動的機械的刺激です、綿棒では刺激が弱く反応が出ないことがあるので、ミラーの縁と充填器の丸い部分で診査しています。痛覚検査はピンセットの先端です。探針は刺さってしまうので使いません。冷感覚は水を含ませた綿棒に冷却スプレーを掛けて氷を作って診査します。温感覚の検査は長年試行錯誤していましたが、今は温度調整の出来るワックスペンを43度に固定して適用しています。もう一つ、趣味というか研究と言うか、電気刺激閾値も調べています。
口腔内は部位により触覚、痛覚、冷感覚、温感覚の閾値が大きく異なり、舌はどの刺激にも敏感です。ところが、歯肉は触覚、痛覚は敏感ですが、冷感覚、温感覚は非常に鈍感です。神経障害性疼痛例では触覚、痛覚の感覚異常に加えて、鈍感であるはずの冷感覚、温感覚も敏感になっている事があります。必ず検査すべきです。感覚異常が認められた場合には後に残る残感覚の有無も確認します。臨床的印象としては自発痛があると残感覚があることが多く、感覚異常があっても残感覚がない場合には自発痛はないように思っています。また、自発痛が消えても、刺激による感覚異常は残ることが多く、感覚異常がなくなることは珍しいです。
経過中に一番変化するのは触覚異常で、最初にallodyniaだったものが、治療によってDysesthesia、Paresthesiaに変化することがあります。一方、前記のように自発痛は消えてもallodyniaが残ることもあります。再診毎に自発痛のVASを毎回記録していて、その変化と感覚検査の結果を照らし合わせています。
治療に関して:診断的局所麻酔で全ての症状が消えて、末梢性100%と判断された場合には、夜間就寝中にステントを用いて2%リドカイン軟膏を貼付しています。温感覚過敏の場合にはTRPV1刺激としてカプサイシン(一味唐辛子、コチジャン、豆板醤、タバスコ)、冷感覚過敏にはTRPM8刺激としてミント(ハッカ油)を追加しています。TRPV1とTRPM8はどちらを刺激しても相互刺激作用があることが判っていて、さらに最近になりヒノキチオールがTRPV1、TRPM8の両方を刺激することが判ったので、ヒノキチオール含有する歯磨きペーストを混ぜる事もあります。口腔内外用薬の使用は全て処方医の責任の元で行ってください。
米国のGaryHeirが局所外用薬についてまとめた論文(Use of compounded topical medications for treatment of orofacial pain: a narrative review J Oral Maxillofac Anesth 2022;1:27 https://dx.doi.org/10.21037/joma-22-10)に帯状疱疹に認可されている外用薬製剤(Lidocaine ointment (5%)、Lidocaine patch (5%)、Capsaicin (0.025–0.075%)、Capsaicin patch (8%))が紹介されています。1999年、米国で初めて承認されたEndo Pharmaceuticals社医療用パップ剤Lidoderm®(Lidocaine patch (5%)帯状疱疹後神経痛治療貼付剤)は日本の四国にある帝國製薬が開発、製造しています。
論文には、上記の帯状疱疹用外用薬製剤の他に、口腔内神経障害性疼痛の治療用に個人の裁量で配合された薬剤(Ketamine4%、Carbamazepine4%、Lidocaine1%、Ketoprofen4%、Gabapentin4%、Pregabalin10%、その他)が紹介されていて、プレガバリン10%が最も効果が高いと書かれています。以前、国際疼痛学会の際に会場に集まった口腔顔面痛専門医の皆さんに口腔内神経障害性疼痛の治療としてリドカインとカプサイシンのどちらを使っているかを質問したら、結果は半々で有効性に差は無いようです。前記したように私の臨床ではリドカイン、カプサイシン、ミント、ヒノキチオール、プレガバリンを状況により適宜併用しています。
再度の確認です、口腔内外用薬の使用は全て処方医の責任で行ってください。
2025年01月13日 13:06