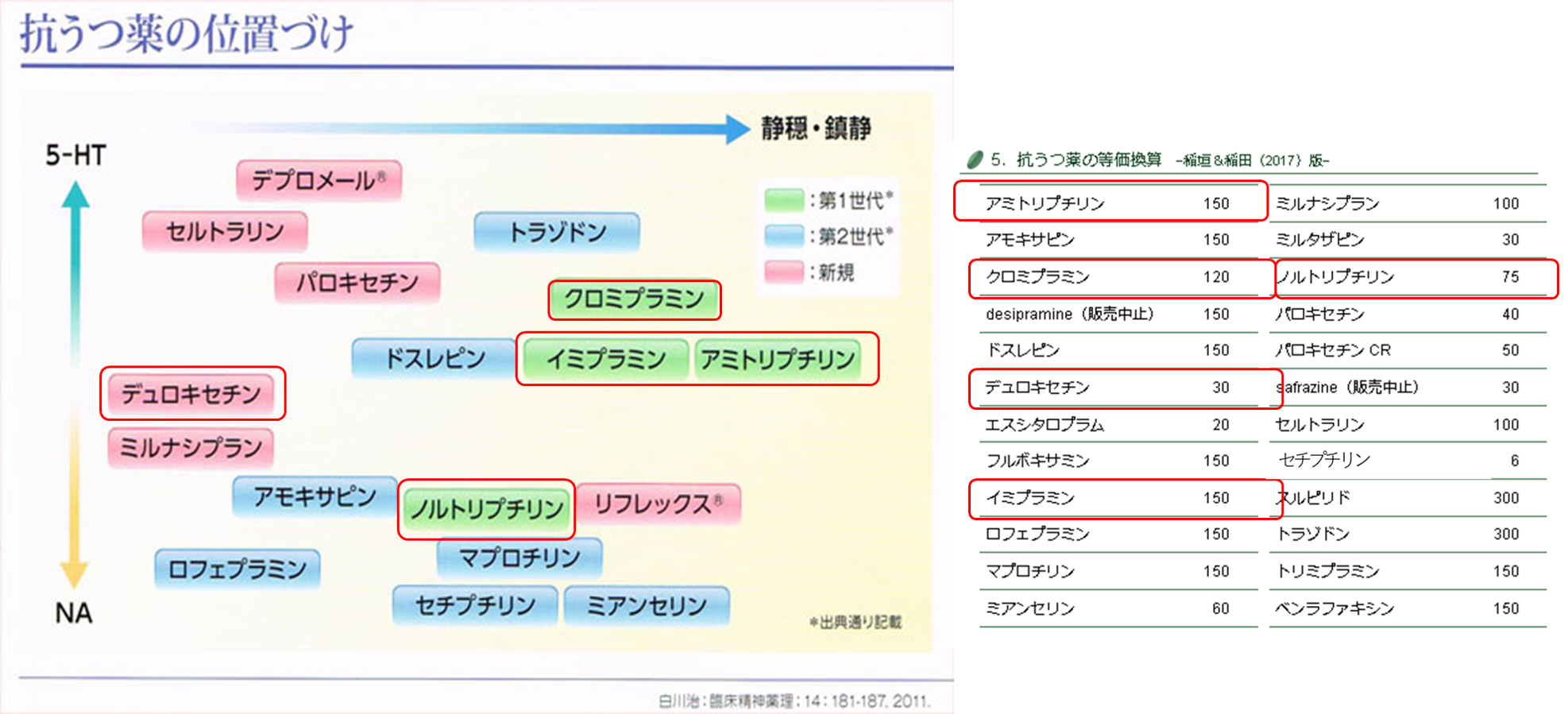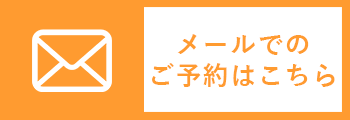案内:顎関節症/口腔顔面痛診査法実技指導セミナー
案内:顎関節症/口腔顔面痛を正しく診断するための診査法実技指導セミナー目的:顎関節症/口腔顔面痛の診断に必要な診査法を実技指導する。
本セミナー開催に当たっての和嶋の考えを記事にしてある。 https://wajima-ofp.com/blog_articles/1743771572.html
構成:1)オンラインでの診査実技の解説(Googlemeet)
2)対面での、少人数、診査法実技指導(会場:元赤坂デンタルクリニック)
3)クリニックでの診療見学(東京、元赤坂デンタルクリニック、札幌、風の杜歯科)
診査法実技指導項目:1)顎関節痛の診査、2)筋・筋膜性疼痛の診査、3)口腔内、顔面の感覚検査、4)12脳神経検査
セミナー開始予定日:2025年5月12日on-line
募集人数:五名限定
受講者に求める事:顎関節症/口腔顔面痛の診査技術の指導であるため、ある程度の基本的知識を持っていること、口腔顔面痛の臨床経験は問わない。
受講料:七万円(申し込み者に振込先を連絡)
応募締め切り:4月25日
応募方法:メール申しこみ、記載事項(氏名、所属、年齢、出身大学、メールアドレス)
申し込み先メールアドレス:wajima.ofp@gmail.com
セミナー予定日時(on-lineは原則第2月曜日20時始まり2時間、対面は10時-16時、診療見学10時-17時適宜)、形式:1)5月12日月曜日:on-line、2)6月9日月曜日:on-line、3)7月14日月曜日:on-line、4)8月31日日曜日:対面、5)9月8日月曜日:on-line、6)日程応相談:診療見学
その他の受講希望者への要望:1)現在、月例で行われている3つの口腔顔面痛関連オンラインセミナー(村岡先生主催慶應OFPオープンセミナー、坂本先生主催OFP-webセミナー、和嶋主催口腔顔面痛オンラインセミナー)を受講することを勧める。 2)本セミナー受講後に日本口腔顔面痛学会主催の口腔顔面痛臨床推論実習セミナーの受講を勧める。
セミナー内容等、受講に当たっての質問は wajima.ofp@gmail.com宛てに送ってください。
2025年04月06日 14:26