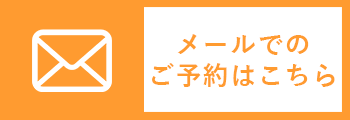顎関節症の本態は身体心理社会モデル
ここ10年、顎関節症の原因が咬合ではなく、心身医学的問題である事が強調され、少しずつ受け入れられてきています。しかし、世界中で咬合が一番大事なんだと、顎関節症の治療のために咬合を変える治療をしている方々もいます。日本各地で顎関節症の治療で有名と言われる方は、大体、咬合治療をしている様です。以前に、「痛みは脳の中」という巻頭言を紹介したように、痛みは末梢の痛みを感じているところに問題があるのではなく、中枢神経系の問題である事が判って来ています。特に慢性疼痛では中枢神経系が痛みを感じ、さらに心理的要因が大きく影響していると言われています。
ここで紹介する論文は、かつては顎関節症の原因は咬合だと強調していた学会(American Equilibration Society)の機関誌の巻頭言を訳したものです。こんなに変わったんだとびっくりしました。少し長いですが読んでみてください。
CRANIO® The Journal of Craniomandibular & Sleep Practice 8 Mar 2024
Editorial The painful mind Sanjivan Kandasamy
顎関節症の治療は、ほぼ1世紀にわたって、多くの論争、議論、さまざまな意見が交わされてきた。その論争は、診断だけでなく、病因や適切な治療にも及んでいる[引用文献1]。さらに最近では、睡眠呼吸障害(SDB)が、独自の論争を展開する別の話題となっており、歯科、医療、および関連保健の専門家が、これらの状態の多くの側面について異なる意見を持つに至っている[引用2,引用3]。
睡眠と痛みが双方向の関係にあることを認めることには、ほとんど異論はない。しかし、論争の多くは、顎関節症の病因に関するこれまでの逸話的で根拠のない信念が、現在ではSDBでも同じであり、したがってSDBの管理の多くは、これまでの顎関節症と同じであるという仮定に関連している。
このような根拠のない病因論的主張は、歯列および骨格の不正咬合の存在、遠心関係の不一致、犬歯の保護咬合の欠如、ブラキシズム、上顎および下顎の後退、狭い上顎、口呼吸、口唇、舌および頭蓋頸部の姿勢の異常など、ほんの数例を挙げるだけでも多岐にわたる[引用1-3]。その結果、多くの臨床家は、顎関節症および/またはSDBに対処するためには、主にこれらの原因の1つまたは複数を取り除く方向に治療を向ける必要があると考えている。
1970年代のプラセボ試験 [引用文献4-7] や、最近では OPPERA (Orofacial Pain: Prospective Evaluation and Risk Assessment) 試験 [引用文献8-11] と呼ばれる大規模な臨床研究など、エビデンスに基づく文献の登場により、顎関節症治療の焦点は、粗雑な歯科的・機械的モデルから、生物心理社会的モデルへと徐々に移行している。偽薬、非閉塞性口腔器具、模擬平衡などのプラセボ顎関節症治療が、生物学的・行動学的に好ましい反応を示したことから、複雑な心と体の相互関係の存在が理解されるようになった。
やがて、専門家の大半は、顎関節症患者を管理するためのより保存的で可逆的な治療法へと進んでいった。さらに、痛みの調節に関するHenry Beecherの初期の観察[引用12]、MelzackとWallの痛みのゲートコントロール理論[引用13]、痛みの神経マトリックス[引用14,引用15]の概念、プラセボの有効性などの結果、医療と歯科の専門家は、痛みのコントロールの中枢調節またはトップダウンの経路が、痛みの経験を管理するための非常に効果的な本質的メカニズムであることを最終的に受け入れ始めました。
私たちは今日、痛みがどのように処理され、知覚されるかについて、より多くのことを知っている。
また、痛みの慢性化や中枢性感作、顎関節症に対する併存疾患の影響、顎関節症になりやすい人の特徴なども、よりよく理解できるようになった。
急性疼痛モデルであれ慢性疼痛モデルであれ、痛みの経験や知覚は認知的・感情的要因に大きく影響される。
この論説は顎関節症そのものに関するものではないが、多くの臨床医が患者の痛み体験の認知的・感情的側面を重視せず、あるいは関与していないことについてのものである。
もし私たちの思考が私たちの感情(そしてやがて私たちの行動)に影響を与えるのであれば、私たちは長い時間をかけて信念体系を構築し、それが最終的に私たちの考え方や日々の対処法に影響を与えることになる。
怒り、不安、恐怖、悲しみなどの否定的な感情とともに、破局視、自分の状況の異常な解釈や意味づけを含む認知の歪みは、人が痛みをどのように受け止め、どのように対処するかに影響を及ぼす重要な役割を担っている [引用16-23]。
多くの臨床医が、スクリーニングのための質問票や/あるいはチェアサイドでのディスカッションという形で、患者の心理的健康について考慮することはあっても、患者が心理的障壁を克服したり、通常の最低限を超えて認知的・感情的にうまく対処できるように手助けしたりするために、実際に患者と一緒に時間を費やしている人はどれほどいるだろうか?
顎関節症の診断や対処法について、エビデンスに基づかない主張を今後もずっと続けていくことになりそうだが、患者の痛みの発生、悪化、持続における心理的要因の役割について、エビデンスに基づいて確立されたことにもっと時間を費やし、日々の臨床に反映させることができるのではないだろうか。 私たちは皆、専門の心理学者や精神科医ではないので、患者の心理的な健康をよりよく管理できるように紹介することは重要だが、これもあまり行われていない。しかし、もし患者が認知的にも感情的にも "トップダウン "で痛み体験をうまく調整できるように手助けをすれば、スプリントを入れたり、錠剤を処方したりする以上に、治療成績がどれほど大きく向上するか想像してみてほしい。さらに良いのは、これらの根本的な影響因子について患者を特定し教育し、認知行動療法(CBT)、リフレーミング、マインドフルネス、リラクゼーション、潜在的にネガティブな行動への気づきなどのスキルを教えれば、患者が自分の痛み体験を管理しやすくなるだけでなく、将来的に苦痛やトラウマを伴う状況に対処しやすくなる可能性がある。 本誌がエビデンスに基づく歯科医療と医学の新たな章に突入する今こそ、エビデンスに基づく心理学的方法を取り入れ、通常の治療を補うことで、治療結果を大幅に改善し、患者が将来痛みと上手に闘う力をつける好機である。私たちは皆、患者さんの辛い心を癒す手助けをすることで、より良い結果を得ることができるのです。