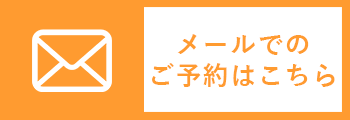国際口腔顔面痛分類(ICOP)、国際頭痛分類第3版(ICHD3)に見つかった大きな誤訳
この度、臨床推論実習セミナーの受講生から非常に違和感のある病名を聞かされました。「帯状疱疹後三叉神経痛」です。帯状疱疹の急性期が過ぎて、慢性化したときに持続的な痛みに発作性の痛みが混じることがあります。通常、これを帯状疱疹後神経痛と呼びます。
ところが、慢性化した持続的な痛みは帯状疱疹後神経痛で、そこに混じる発作性の痛みの病名は「帯状疱疹後三叉神経痛」が適切だろうという意見でした。なるほどと思うとともに大きな違和感がありました。そんな病名あったかと思って確認したら、国際口腔顔面痛分類(ICOP)は国際頭痛分類第3版(ICHD3)ともに確かにありました。
「帯状疱疹後三叉神経痛」を字面の通りに解釈すると、帯状疱疹後に起こる、あるいは帯状疱疹に罹患したことが原因で起こる三叉神経痛となります。もっともらしいのですが、これは大間違いで、「帯状疱疹後三叉神経痛」は誤訳です。
「帯状疱疹後三叉神経痛
Trigeminal Post-Herpetic Neuralgia」は三叉神経痛の下分類では無く、三叉神経ニューロパチーの下分類として、帯状疱疹による有痛性三叉神経ニューロパチー、外傷後三叉神経ニューロパチーなどと並列に分類されています。つまり、三叉神経痛の下分類ではないのです。
ICHD3βでは明らかにニューロパチーが生じているということで「帯状疱疹後有痛性三叉神経ニューロパチーPost-Herpetic Trigeminal neuropathy」となっていました。しかし、やはり、帯状疱疹後神経痛Post-Herpetic Neuralgiaという用語が普及していることから、ICHD3では再度、改訂されました。ここで誤訳が発生したのです。
帯状疱疹後三叉神経痛の原文はTrigeminal Post-Herpetic Neuralgiaでした。ICHD3βの帯状疱疹後有痛性三叉神経ニューロパチーPost-Herpetic Trigeminal neuropathy」とではtrigeminalの位置が異なります。Trigeminal Post-Herpetic Neuralgiaでは敢えて先頭にtrigeminalを置いてあります。
中間神経の項に類似の分類があります。有痛性中間神経ニューロパチーの下分類に、帯状疱疹後中間神経痛があり、その英文はPost-Herpetic Neuralgia of nervus intermediusです。帯状疱疹後中間神経痛も誤訳です。
帯状疱疹後三叉神経痛Trigeminal Post-Herpetic Neuralgia
帯状疱疹後中間神経痛Post-Herpetic Neuralgia of nervus intermedius
並べて見ると、同じ分類なのに英文に統一性がないのも気になりますが、敢えて帯状疱疹後神経痛という病態を元に英文と日本文を修正するなら、
Trigeminal Post-Herpetic Neuralgia 三叉神経帯状疱疹後神経痛
Nervus intermedius Post-Herpetic Neuralgia 中間神経帯状疱疹後神経痛
これが適切と思います。
国際頭痛分類第4版への改訂が進められているそうです、発刊されるとすぐに日本語訳が出来ますので、間違いが出ないように担当の先生に今から連絡しておこうと思います。
2025年09月26日 09:17