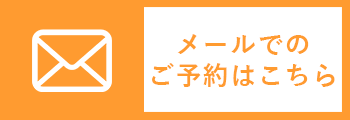口腔顔面痛を正しく診断 筋筋膜性疼痛を抜髄で神経障害性疼痛
私の臨床で最も気になる病態、イライラする治療経過の症例を紹介します。筋・筋膜性疼痛絡みの打診痛、自発痛、歯肉の感覚障害という例です。多くは複数回の根管治療を経て来院します。気になるのは、筋・筋膜性疼痛の痛みで神経系が前刺激されたところに抜髄等の侵害刺激が加わって侵害受容性疼痛が神経障害性疼痛が加わってしまったのだろうと思われること。気になるのは、筋・筋膜性疼痛を見つけていれば発症を防げたのではないか、歯原性にこだわって歯内療法を繰り返す前に気づけなかったのか、紹介する前に根充せずに根尖孔からの薬物療法のルートを残してほしかった、というイライラも加わります。
筋・筋膜性疼痛の侵害受容性疼痛に抜髄刺激により神経障害性疼痛を重複させてしまう事を予防する為にも、正しい診断が必要です。
症例2:58歳男性
主訴:4年前に下顎右側7の抜髄以来、持続性の痛みがある。抜髄以来、計三回の根管治療受けたが改善しない。3回目の根管治療を行った歯内療法専門医から非歯原性歯痛の診査依頼
抜髄時の経緯は、充填治療を行った後、冷水痛、咀嚼時痛が強く抜髄したことから歯原性であった事が明らか。しかし、抜髄後も持続痛は改善しなかった。その後、同医に再根管治療を受けたが改善せず、1年前に歯内療法専門医に3回目の根管治療を受けた。
心理テスト:HADs(不安3点、うつ6点)、PCS(反芻16点、無力感8点、拡大視5点)
睡眠障害診査:問題無し
既往歴と内服薬:4年前最初のENDO治療とほぼ同時期に、会社内のトラブルで不安障害が生じて、精神科受診。それ以来、抗不安薬メイラックス(ロフラゼプ酸エチル1mg)、睡眠薬(トリプタノール10mg2T、トラゾドン5mg )服用中、起床時に眠気が残り、減量検討中。現在、会社内のトラブルは解消し、不安の自覚症状も改善している。
局所診査:
- 歯原性、非歯原性の診査:デンタル、パノラマレントゲン下顎右側7根尖透過像無し、打診痛+、以上から歯原性を完全否定しきれず。他に痛みの原因と思われる異常認められず。
- 感覚検査:下顎右側7頬側歯肉に触覚Allodynia残感覚あり、痛覚感覚異常なし、冷感覚、温感覚-感覚異常なし
- 脳神経検査:上記三叉神経右側第3枝感覚異常以外異常認められず。
- 筋触診:右側咬筋肥大+、硬結++、圧痛++関連痛あり、主訴、何時もの痛み再現、歯痛再現、右側咬筋肥大+、硬結+、圧痛+関連痛なし、右側側頭筋肥大+ 硬結+ 圧痛+ 関連痛なし、右側後頸部圧痛+、右側胸鎖乳突筋硬結+ 圧痛+。
- 顎関節診査:ROM51mm、左右側下顎頭滑走正常 牽引、圧迫誘発テスト痛みなし 左右茎状突起腫大+ 圧痛+ 全身Hypermobilityあり
- 咬合状態:明らかな異常なし
- 診断的局所麻酔:歯根膜注射により打診痛完全消失、頬側歯肉感覚異常消えず。頬粘膜浸潤麻酔によりallodynia消失。歯根膜注射、頬粘膜注射によっても持続痛は約50%残った。
考察:現在につながる持続痛の発症当時の記憶は明らかで、術前痛みはなかったがカリエス充填処置後に冷水痛が強く、咀嚼時痛もあったために抜髄となり、冷水痛は消えたが持続痛が続いたことに始まったとのことであった。その持続痛が多少の変動はあったようであるが、ほぼ現在の痛みにつながっているとのことであった。
抜髄にもかかわらず、何故直後に持続痛が残り、続いているのかが現在の持続痛の原因解明につながると思う。
打診痛は歯原性の可能性はゼロでは無いが、最終歯内療法後1年経過してレントゲン的に異常が認められないことから、非歯原性歯痛として考察する。診断的局所麻酔の結果から、3回の根管治療による末梢刺激の結果として末梢および中枢感作が生じていることが考えられる。
また、現在右側咬筋に明らかな筋・筋膜性疼痛がある事から、抜髄以前に自発痛はなかったが右側咬筋に不顕性筋・筋膜性疼痛が生じ、痛み刺激により末梢、中枢感作が生じていた可能性がある。歯痛は生じていなくても、現在認められる様に歯肉に感覚異常を生じていた可能性もある。
このような神経系の状況下に抜髄処置が加わったことにより中枢神経系が刺激されて持続痛になってしまったと推定される。抜髄処置は局所麻酔下で行われるので処置中の侵害刺激は中枢には伝わらないはずであるが、歯髄に至る神経は切断されたことにより、如何にも外傷性神経障害性疼痛の状況に至ったことが考えられる。
完全なる推論:筋・筋膜性疼痛で神経系が刺激された状況に抜髄処置が加わった事による神経障害性疼痛の発生
現症として持続痛、打診痛、歯肉の感覚障害が認められる、診断的局所麻酔により打診痛、歯肉感覚障害は消失するが持続痛は半分残ることなどからの完全なる推定です
歯内療法術後痛が問題になり、その原因がいろいろ考えられています。1)当該歯の抜髄処置前の3ヶ月以上の持続した痛み、2)歯以外の部位に長期の持続痛があった、3)慢性痛の既往がある、等が挙げられます。個々に含まれない原因として、4)後に関連痛を生ずる筋・筋膜性疼痛が抜髄以前からあった可能性です。筋・筋膜性疼痛の作用としては、本症例の様に不顕性で関連痛は生じていないが当該神経系を刺激していたところに抜髄処置が加わり神経障害性疼痛になった、もう一つは、筋・筋膜性疼痛の関連痛である事が正しく診断されずに、歯原性歯痛として抜髄されてしまい筋・筋膜性疼痛が神経障害性疼痛なってしまったことが推定されます。
2025年01月07日 15:27