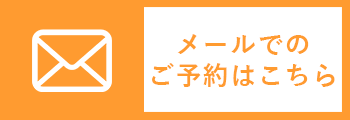痛覚変調性疼痛が話題になってから、私の関心は従来の心因性疼痛と痛覚変調性疼痛の関連性と心因性という用語はなぜ用いられたのか、どのような事を意味していたのか、実際の臨床の中で該当する患者さんを探して、何が心因性なのか、痛覚変調性は何を意味するのか確かめてみることです。天の邪鬼な性格故に皆さんの痛覚変調性疼痛理解とは別な方向に進んでいます。
解釈モデルを知り、解釈モデルをホワイトボードに例えて、今現在、患者さんがどんな事を考えているのかを、ホワイトボードに何と書かれているかを確認するよう務めています。その結果、私の診査診断の結果の治療方針とズレの有無が明らかになる。ズレがある場合、なぜそのように考えるようになったのか、うつ病に代表される歪んだ認知、考え方があるのか等が、カルテに文字化されて書かれ、明らかに認識出来る様になりました。
その中で気になるのは、慢性痛の患者さんは大きな不安感を抱えていることです。
始まりは痛み、多くの痛みは痛みを感じる部分に痛みの原因があり、医者に診てもらえば診断が決まり、治療するとすぐに治ると思っています、そのように解釈モデルには書かれていました。
歪んだ認知、考え方によるズレという前に、ズレを生む大きな問題が目の前にありました。口腔顔面痛の代表的な疾患である非歯原性歯痛では痛みの感じる部分と痛みの原因部分が異なる異所性疼痛なのです。我々口腔顔面痛専門医は当たり前になってしまっていますが、自分で改めて考えても変ですし、患者さんが混乱するのは当然の事と思います。
このような混乱を生む状況をしっかり把握し、どうすれば混乱を防げるかの対策を考えています。
患者さんが痛みを訴える部分には原因になるような異常が認められない、ここで一般診療では原因不明ということで診断が進まなくなります。これによって、「ここに原因があるのだから、ここを治療すればすぐにでも治るのに」という患者さんの解釈モデルと一致しない部分が出てきます。その結果として患者さんの認知は変わり、「自分の言っている事が信じてもらえない、だから解決に向かわない、どうすれば良いのか、別な病院探さなければならないのか」、そして気分、感情は「めちゃくちゃ不安」となります。非歯原性歯痛だけで無く、様々な痛みの治療を受ける過程で解釈モデルと診断、治療方針にズレが生じていると患者さんが不安を感じることが多いようです。
この不安感によって身体反応、身体感覚として痛みが強く感じられることとなります。私はこの部分が心因性疼痛であり、痛覚変調性疼痛の局面だろうと思います。
この状況での効果的な治療は、痛み治療よりも不安を和らげることです。痛み診査、治療の経過の中で生じた解釈モデルの混乱、ズレについて、患者さんにとって腑に落ちる説明が得られると不安が解消されます。安心だけでは不安が解消されずに睡眠障害を伴う場合には睡眠導入剤、抗不安薬が有効なこともあります。
最近診た典型的な3例を概説します。
症例1 35歳女性 HIFU(ハイフ)という美容施術を受けた後の咬筋筋・筋膜疼痛となり、歯痛が生じて歯科受診 プラスアルファ
HIFU(ハイフ)とは、High Intensity Focused Ultrasound(高密度焦点式超音波療法)(美容外科からの引用:お肌への負担を限りなく抑えながら高密度の熱エネルギーをお肌の奥まで届かせます。肌内部では受けた損傷を治そうと、コラーゲンが増生されます。この作用によりお肌が内側から引き締められ、お顔を引き上げていきます。)
ハイフを受けた後、頬部に痛み、歯痛も生じて、歯科受診。患者さんにとってハイフで頬部が痛いのは想定内、しかし、歯痛も関連するとは全く思わず。歯痛がハイフにより生じた咬筋筋・筋膜疼痛の関連痛とは考えなかった。異所性疼痛ですから当然と言えば当然、 ところが歯科医も診断できず。知覚過敏の診断で、繰り返し知覚過敏処置と負担過重軽減のために咬合調整。咬むと咬合面がしみると言う事で咬合面にもコーティング、当然、早期接触が生じ、かみ合わせがおかしいという異和感、そこを削る、また、しみるの繰り返し。患者が説明を求めると、毎回違った説明と新たな治療法提案、患者は不安感が高じて、自ら心療内科受診、そこで抗不安薬が処方され服薬、痛みは日ごとに改善してきた。
しかし、頬部の鈍痛、当初はハイファの術後痛と理解していたが、こんなにも続くものかと不安が強くなってきた。また、歯痛があり、冷水はしみなくなったが噛み方によりギックと激痛が生ずることも不安で受診した。
和嶋の理解と患者説明:歯の持続痛は筋・筋膜疼痛によるものであること、これは最初に遡って、筋緊張の準備因子があったところにハイフの筋膜舳の刺激により筋・筋膜疼痛が生じて頬部痛と関連痛として歯痛が生じた、現在の頬部痛、歯痛もそれが続いていることを説明した。
毎回違った診断と新たな治療法の提示に納得出来なかったことと不安感の高まったことにより痛みが強く感じられた事、患者自らの判断で心療内科受診して、今も抗不安薬を服用しているのは適切だったと思われることを説明した。かみ具合によりギクッとした痛みは咬合調整の結果、象牙質が露出して生じているであろう事を説明し、筋・筋膜疼痛、象牙質露出への治療法を提示した。
症例2.上顎前歯部にインプラント、頭出しして、さあ上部構造と言うときに痛みで中断を余儀なくされた。何本かの中の1本のインプラントがネジを締めたり、暫間冠を装着しようと力をかけると激痛が生ずるということで数回挑戦したが痛みが出る事に恐怖感が出てしまい、さらに持続痛も生じて上部構造の作成を一時中断。時期を同じくして、全身状態が悪化、内科の主治医を受診したが内科的には異常なし、大学病院脳神経外科受診、MRI等で検査するが異常なし、口腔外科を受診、筋・筋膜疼痛の診断で筋マッサージの指導を受けた。一向に改善せず、最近は病院に行くために車に乗ることすら出来ず、治療は何も受けていない。家ではほとんど横になっている状態で日常生活が出来ないとのこと。ご主人からの電話相談を受けて、以上の経過を聞いた。インプラント治療中に生ずる痛みがどうしても耐えられないことへの不安感、恐怖から痛みが出て、全身状態にも影響していることを推定して、精神科受診を勧めた。後日電話があり、以下の経過を受けた。精神科受診して、睡眠導入剤と抗うつ薬を処方された、抗うつ薬は副作用のための一日しか服用できなかったが睡眠導入剤が効果的で、睡眠が改善された。約1ヶ月経過して、持続痛は改善し、日常生活が出来るほどになり、元通り自分で車を運転して買い物に出かけられるまでに回復したとの事であった。
和嶋の理解:睡眠導入剤により睡眠が改善され、不安の改善に役立った。持続性疼痛がないこと、治療が中断され、インプラント部に触れなければ痛み刺激はないことにより次第に改善に向かったと推定される。
症例3:35歳男性 2ヶ月前に上顎左側6の歯肉痛
1年前から上顎左側大臼歯部に異和感、上顎左側6は2年前に痛み治療の為に意図的再植、1年間痛み無かったが1年前から痛み再発、次第に増悪。4ヶ月前にかかりつけ医で歯周炎と言う診断でFlap手術を受けた。術後痛みが強く、再診、再植した歯が急性炎症を起こしていると言うことで、再度意図的再植術、術後、痛みは増悪、1週間後に抜歯、さらに痛みは強くなり、持続痛に経過中に発作痛が加わった。口腔顔面痛専門医を数軒受診、神経障害性疼痛、筋・筋膜疼痛、の診断、神経障害性疼痛の治療として処方されたトリプタノール10mgは翌日眠くて継続出来ず。大学口腔外科では抗菌薬処方。筋・筋膜疼痛専門整形外科受診、咬筋にトリガーポイントインジェクション、神経内科受診神経学的異常なし、リボトロリール処方されたが杭痙攀薬と書かれていたので服用せず、次にタリージェ処方され、服用したらふらつきで中止。漢方専門医受診、何種類かの漢方薬服用したが効果無し、脳神経外科受診、画像検査異常なし、三叉神経痛の診断でカルバマゼピン処方されるも、ふらつきで中止。次の内科でヂュロキセチン処方、吐き気で中止。大学ペインクリニックで眼窩下孔にブロック注射、効果は不明、その日から突発性難聴で耳鼻科受診、ステロイド治療を受ける、同日に母親が服用しているバランス(抗不安薬)10mgを服用し始める。バランスは以前にものストレスが強い時に服用したことがあった。徐々に痛みが改善。10日後に当クリニック受診、現在は発作痛なし、持続性の2/10鈍痛がある。上顎左側歯肉にallodynia、Hyperalgesiaあり、顔面左側v2に触覚鈍麻、痛覚過敏あり、咀嚼筋圧痛無し。現在、バランス(抗不安薬)のみ継続服用中。
気になった事、最初はChairに座って、握りこぶしををつくり、身体を強ばらせていた、これまでの治療経過を聞いて、想定される原因と症状のストーリーを話していると、実は、実は、といくつもの新しい情報 そして、診療が終わったときには握りこぶしがほぐれていた。
和嶋の理解と患者説明:1)何らかの器質的痛みがあった可能性、2)そこに切開の外科的侵襲が加わった。腫れたとは言っていないので、感染、化膿は無かった様である。3)痛みへの不安により痛覚変調性して、痛み増悪、4)そこに意図的再植、抜歯外科処置の侵害刺激が加えられ、痛みは増悪し不安が増す。5)痛みが強いので、口腔顔面痛専門医を始め、複数の痛み関連診療科を受診するも改善せず、さらに不安が増し、痛みは増悪。6)ストレス性と思われる特発性難聴発症、改善因子として7)大学ペインクリニックで眼窩下孔にブロック注射と8)自分判断でバランス服用、を説明した。
現在残る症状として、感覚障害がある、三叉神経痛とは思えない、筋・筋膜疼痛でもないこと、眼窩下孔にブロック注射と抗不安薬のバランス服用が奏功した可能性がある事を説明した。今回の経過中大きな不安が生じたことは何らかの精神的素因が考えられるので、バランス服用の管理も兼ねて精神科受診を勧めた。
2022年08月03日 18:12