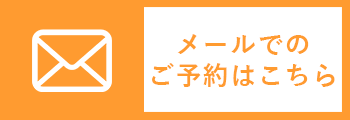口腔診断学会・口腔内科学会共催学会臨床推論シンポジュウム
臨床推論シンポジュウム9月6日、仙台で開催される口腔診断学会・口腔内科学会共催学会において、口腔顔面痛学会コラボレーション・シンポジウムとして、「日々の診療に臨床推論を根付かせる~これからの歯科医師にどう教育するか~」が行われます。私は企画提案者として座長を務めます。
歯学部教育の指標となる「歯学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版)に臨床推論が新規作用され、令和6年入学生から教育する事が求められています。
臨床推論で求めているのは、臨床経験に基づいて行われる直感的思考(パターン認識法)から仮説演繹法に代表される分析的臨床推論を学習することです。本文には、主要な症候から鑑別すべき主な原因疾患が示され、その説明として、「症候から想定すべき代表的な原因疾患例等を記載したが、症候に該当する疾患を網羅しているわけではない。臨床推論では可能性のある症候や病態から原因疾患を鑑別診断するプロセスが重視され、原因疾患を単純に全て暗記することを期待しているものではない。」と記載され、明確に分析的臨床推論を学習することを求めています。
歯学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版)抜粋
E-3-2 臨床推論 口腔・顎顔面領域の主な症候から病態生理学的に発症原因を推論し、分類、鑑別診断できる基本的能力を身に付ける。
学修目標:
E-3-2-1 主要な症候について原因と病態生理を理解している。
E-3-2-2 主要な症候について鑑別診断を検討し、診断の要点を説明できる。
E-3-2-3 臨床実習の現場で主訴から診断推論を組み立てられる。
E-3-2-4 臨床実習の現場における疾患の病態や疫学を理解している。
口腔顔面痛学会では10年以上前から痛みの診断方法として仮説演繹法を推奨し、その習得のために実習セミナーを行って来ました。日本口腔顔面痛学会認定医、専門医は痛み診断のための仮説演繹法をマスターし、痛み治療に活用しています。ところが、歯科全般としては歯学部教育のなかで臨床推論を学習する機会が無かったために、卒業後も各自の臨床経験に基づいて直感のようにパターン認識法で診断しています。臨床経験が多ければ直感でも正しい診断が出来ますが、如何に一つ一つの症例を解析して蓄積するかによって診断の正確さが変わります。少しでも症例の振り返りをすると症例の特徴が解析され整理されて記憶に残り、次に同じ様な症例を診たときにスムースに記憶が呼び起こされます
診断法の教育の場面ではパターン認識法は役に立ちません、研修医が指導医と一緒に臨床に立ち会っても、指導医の頭の中で考えていることは伝わってきません。研修機関における診断指導では診断のプロセスを可視化する事が必要です、その可視化のフォーマットの一つが仮説演繹法です。
https://wajima-ofp.com/blog_articles/1728088294.html
2025年09月04日 13:30