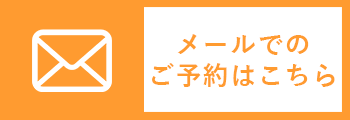感覚は双方向という話し、痛みは感覚か解釈か、と言う話
感覚は双方向という話しと痛みは感覚か解釈か、と言う話以前、加藤総夫先生の講演で視覚、聴覚は双方向だという話しとデモを見せてもらったことがあります。漠然と見えているモノと意図的に見ようとした時、探そうとしたときの異なって見える、同様に聞こえている音を意図的に聞こうとしたときに聞こえる音が違って聞こえると言う話しだったと思います。味覚も同様だと思います、何気なく食べている料理のなかで、この味は?と意識するといろいろな味がはっきり感じられます。その結果、美味しく感じるかどうかは保証しませんが。
普段、舌が特別の敏感だとは感じられませんが、触覚、痛覚、冷温覚とも非常に敏感な組織です。歯の鋭縁や凹凸、咬頭の凸凹、充填物の段差など、また、口蓋皺襞の凸凹、舌乳頭のザラザラなど、それまで何も気にならなかったモノが、いったん気になり出すと、如何にも探しているように全て異常と感じてしまいます。
感覚が双方向と言っても、感覚を伝える神経線維を伝わる信号は全て末梢から中枢に向かい、信号が逆行して探す訳ではありません。中枢に向かう信号の中から目的とする信号を脳が選別し、拡大して捉えることにより脳から末梢の感覚器に探しに行っているように感じられるのだと思います。要するに、求心性に脳に伝わった感覚を脳が解釈しているとも言えます。
我々は診査で口腔内を診るときに、見慣れた口腔内で間違い探しのように、異常な所見がないかどうかを探します。異常所見には違和感で判別できます。
患者さんが何らかのきっかけで口腔内を見ると、見慣れないモノがいっぱいあります。よくある例が口蓋隆起です、ある日突然、上顎がヒリヒリ、よく観たら大きな出っ張りがある、気になってしまいどうしようも無い。昨日までは何もなく突然に出来た(本当は偶然見つけた)ので、きっとアゴのガンに違いないと訴えます。確かに大きな口蓋隆起で、よく今日まで気にならずに過ごしてきたモノだと思える位の大きさです。ところが、全く気にならずに今日まで過ごしてきたのです。このように大きな凸凹があっても、舌にとっては慣れ親しんだ凹凸だったのですが、いったん気になると、歯が出っ張っている、かみ合わせが悪いからだと異常として捉えてしまいます。
同様にいっぱい毛が生えている、それが一様ではない。これはガンではないか、そう思ったら舌に痛みも感じると受診する人もいます。舌に毛が無かったら、まるで因幡の白ウサギのように、しみて、しみて大変ですよ、舌を守るために毛が生えているのですよと正常な舌の写真(本当は私の舌をべーっと見せたいが)を見せて説明したら、納得できて帰りには痛みも消えていました。
痛みは本来、身体を傷害から守るための警告信号で、生きるために必要な事です。急性の痛みのほとんどは原因を取り除けば痛みが消えます。問題は慢性化した痛みです、慢性化した痛みは痛みの原因とは離れたところで続いています、まるで、ハシゴを外されたよう。その理由の一つが、長い間、痛みが続くと痛み神経系が刺激されて過敏な状態になってしまい、原因が無くなっても過敏な状態は続きます。そして、気になって何時も痛みを探しています。このような状況の慢性痛の患者さんへの説明によく使うフレーズを紹介します。試験勉強の為に毎日復習していると試験で満点、ところが、復習しないと良い点数がとれない、試験のためには復習が効果的だが、気にして痛みを探し続けると記憶を呼び戻すことになり最悪です。それではどうすれば良いか、気にしないようにしても気になってしまいます、止めることは出来ないのです。意識を他に向けることです、痛みの復習では無く、他の楽しいことを考える、痛いところを使った動作をする、これにより意識が他に向いて、痛みが感じなくなります。これがマインドフルネスです。
2025年04月24日 14:24